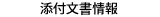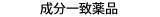メキシチール点滴静注125mgの用法・用量
- 静脈内1回投与法:
- 通常成人には1回1管(メキシレチン塩酸塩として125mg、2~3mg/kg)を必要に応じて生理食塩液又はブドウ糖液等に希釈し、心電図の監視下に臨床症状の観察、血圧測定を頻回に行いながら5~10分間かけ徐々に静脈内に注射する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
- 点滴静脈内投与法:
- 静脈内1回投与が有効で、効果の持続を期待する場合に、心電図の連続監視下に臨床症状の観察、血圧測定を頻回に行いながら点滴静脈内注射を行う。通常成人には、次のいずれかの方法で投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
- ①.シリンジポンプを用いる場合:1管(メキシレチン塩酸塩として125mg)を必要に応じて生理食塩液又はブドウ糖液等に希釈し、1時間にメキシレチン塩酸塩として0.4~0.6mg/kgの速度で投与する。
- ②.微量調整用の自動点滴装置又は微量調整用の輸液セットを用いる場合:1管(メキシレチン塩酸塩として125mg)を必要に応じて生理食塩液又はブドウ糖液等500mLに希釈し、メキシレチン塩酸塩として0.4~0.6mg/kg/時(体重50kgの場合1分間に1.3~2.0mLに相当)の速度で投与する。
メキシチール点滴静注125mgの効能・効果
頻脈性不整脈<心室性>。
メキシチール点滴静注125mgの副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 1.重大な副作用:
- 1)中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、紅皮症(いずれも頻度不明)。
- 2)心停止(0.4%)、完全房室ブロック(0.2%)、幻覚、心室頻拍、ショック、錯乱(いずれも頻度不明)。
- 2.その他の副作用:
- [1]循環器:(1~5%未満)血圧低下、(1%未満)動悸、胸部圧迫感、徐脈、(頻度不明)QRS延長、洞停止。
- [2]消化器:(1~5%未満)悪心・嘔吐、(1%未満)口渇、胃重圧感、(頻度不明)胸やけ、腹部膨満感、食欲不振、胃部不快感・腹部不快感。
- [3]精神神経系:(1~5%未満)頭がボーとする(3.8%)、口のしびれ感・舌のしびれ感等(3.6%)、めまい(2.1%)、(1%未満)頭痛、発汗、眠気、痙攣、耳鳴、顔面潮紅、(頻度不明)せん妄、運動失調。
- [4]過敏症:(1%未満)手掌そう痒感。
- [5]肝臓:(1%未満)AST上昇、ALT上昇、(頻度不明)γ-GTP上昇、黄疸。
- [6]血液:(頻度不明)血小板減少。
- [7]その他:(1~5%未満)熱感・灼熱感(3.0%)、(1%未満)鼻閉、血管痛、倦怠感。
メキシチール点滴静注125mgの使用上の注意
【禁忌】
重篤な刺激伝導障害(ペースメーカー未使用の2~3度房室ブロック等)のある患者[刺激伝導障害の悪化、心停止を来すことがある]。
【重要な基本的注意】
- 1.本剤の投与に際しては、必ず心電図の連続監視と頻回の臨床症状の観察、頻回の血圧測定等を行うこと。PQ延長、QRS幅増大、QT延長、徐脈、血圧低下等の異常所見が認められた場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。
- 2.紅斑、水疱・びらん、結膜炎、口内炎、発熱等があらわれた場合には中毒性表皮壊死症(TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、紅皮症の前駆症状である可能性があるため、紅斑、水疱・びらん、結膜炎、口内炎、発熱等があらわれた場合には投与を中止し、直ちに皮膚科専門医を受診させる等適切な処置を行うこと(TEN:Toxic Epidermal Necrolysis)。
- 3.頭がボーとする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。
- 4.経口投与が困難な場合や、緊急の場合に使用すること。なお、経口投与が可能となった後は、速やかに経口投与に切りかえること。
【合併症・既往歴等のある患者】
- 1.重篤な心不全を合併している患者:完全房室ブロックを来すことがある。
- 2.完全房室ブロックのある患者:一過性心停止を来すことがある。
- 3.基礎心疾患(心筋梗塞、弁膜症、心筋症等)のある患者:心機能抑制や催不整脈作用が出現することがある。基礎心疾患があり心不全(心筋梗塞があり心不全、弁膜症があり心不全、心筋症があり心不全等)を来すおそれのある患者では、少量から開始するなど投与量に十分注意すること(心室頻拍、心室細動等が発現するおそれが高い)。
- 4.軽度刺激伝導障害(不完全房室ブロック、脚ブロック等)のある患者:刺激伝導障害を悪化させることがある。
- 5.著明な洞性徐脈のある患者:徐脈を悪化させることがある。
- 6.心不全のある患者:心不全を悪化、不整脈を悪化・誘発させることがあり、また、本剤の血中濃度が上昇することがある(心室頻拍、心室細動が発現するおそれが高い)。
- 7.恒久的ペースメーカー使用中あるいは一時的ペーシング中の患者:異常が認められた場合には直ちに減量又は投与を中止すること(本剤は心臓ペーシング閾値を上昇させる場合がある)。
- 8.植え込み型除細動器<ICD>使用中の患者:十分に注意して経過観察を行うこと(ICDの除細動閾値を上昇させる場合がある)。
- 9.低血圧の患者:循環状態を悪化させることがある。
- 10.パーキンソン症候群の患者:振戦を増強させることがある。
- 11.血清カリウム低下のある患者:不整脈を誘発させることがある。
- 12.他の抗不整脈薬による治療中の患者:少量から開始するなど投与量に十分注意すること(有効性、安全性が確立していない)。
【腎機能障害患者】
- 1)重篤な腎機能障害のある患者:本剤の血中濃度が上昇することがある。
【肝機能障害患者】
- 1)重篤な肝機能障害のある患者:本剤の血中濃度が上昇することがある。
【妊婦】
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
【授乳婦】
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること(母乳中へ移行することが報告されている)。
【小児等】
小児等に対する臨床試験は実施していない。
【高齢者】
少量から開始するなど投与量に十分注意すること(肝・腎機能が低下していることが多く、また、体重が少ない傾向があるなど副作用が発現しやすい)。
【相互作用】
本薬は主に肝臓のチトクロームP-450のCYP2D6及びCYP1A2で代謝を受ける。
- 2.併用注意:
- [1]リドカイン、プロカインアミド、キニジン、カルシウム拮抗剤、β受容体遮断剤[本剤の作用が増強することがある(両剤の陰性変力作用と変伝導作用が相加的又は相乗的に増強することがある)]。
- [2]肝薬物代謝酵素機能に影響を与える薬剤(特にチトクロームP-450系のCYP1A2及び2D6に影響を与える薬剤)[本剤の血中濃度に影響を与えるおそれがある(チトクロームP-450(CYP1A2、2D6)による本剤の代謝が影響を受けるおそれがある)]。
- [3]アミオダロン[torsade de pointesを発現したとの報告がある(機序不明)]。
- [4]シメチジン[本剤の血中濃度が上昇することがある(シメチジンによりチトクロームP-450の薬物代謝が阻害され本剤の血中濃度が上昇することがある)]。
- [5]リファンピシン、フェニトイン[本剤の血中濃度が低下することがある(本剤の代謝が促進されることがある)]。
- [6]テオフィリン[テオフィリンの血中濃度が上昇することがある(本剤はテオフィリンに比べ、チトクロームP-450への親和性が強く、テオフィリンの代謝が抑制される)]。
- [7]尿のpHをアルカリ化させる薬剤(炭酸水素ナトリウム等)[本剤の血中濃度が上昇することがある(アルカリ性尿は、本剤の腎排泄を抑制する)]。
- [8]尿のpHを酸性化させる薬剤(塩化アンモニウム等)[本剤の血中濃度が低下することがある(酸性尿は、本剤の腎排泄を促進する)]。
【過量投与】
- 1.症状:過量投与の結果、副作用の項に記載した悪心、眠気、徐脈、低血圧、痙攣、錯乱、心停止等の症状の他に、知覚異常、意識障害、不穏、妄想、心室細動、呼吸停止があらわれたとの報告がある。
- 2.処置方法:
- 1)過量投与時、重篤な徐脈、重篤な低血圧の場合、必要に応じアトロピンを使用する等適切な処置を行うこと。
- 2)過量投与時、痙攣等があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、ベンゾジアゼピン系薬剤等の投与、人工呼吸、酸素吸入等必要に応じて適切な処置を行うこと。
【適用上の注意】
- 1.薬剤投与時の注意:
- 1)本剤は静脈内注射にのみ使用すること。
- 2)通常の成人用点滴装置を用いて点滴静注をしないこと。
- 3)静脈内投与によりときに血管痛を起こすことがあるので、注射部位、注射方法等に十分注意すること。
【保管上の注意】
室温保存。